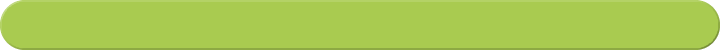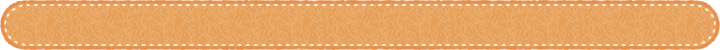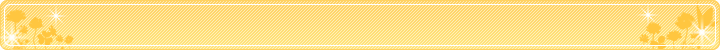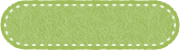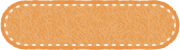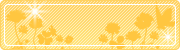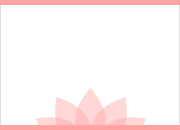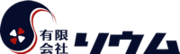- ホーム
- お月さまだより
お月さまだより
2015/09/12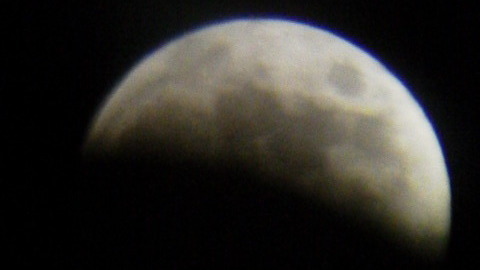
十六夜、十七夜、十八夜・・・
十六夜(いざよい)は満月の翌日に現れます。
満月より50分遅れで出てくるため、いざよう(ためらう)ように出てくると、この名がつきました。
不知夜月(いざよいづき)などとも言われ、一晩中出ているので、こんな名がついたのかもしれません。
ちなみに鎌倉時代に阿仏尼が書いた「十六夜日記」は、
当初題名が付いていなかったのですが、
日記が十月十六日から始まるため、後世の人がこの名を付けたそうです。
またその翌日、17日の月はさらに遅く昇ります。
そのため立待ち(たちまち:立って待つほど) の月と呼ばれます。
この時期は、満月にピークを迎えた事・成就した事を更に発展させるべき時期です。
ひかえたほうがよい事
満月を過ぎたら夜更かしや不摂生はなるべく避け、
仕事はダラダラ残業を続けても、効率が悪くなるだけ。ながら残業は避けること。
人に対しては、閉鎖的になってはダメなようです。
おすすめはダイエットです。
身体は70%が水分。月の影響を受けているはずです。
ダイエット実行は、満月が終わってから朔(新月)までの月が欠けていくときに効果があります。
(逆に満ちていくときは、生命力がみなぎり、ダイエットに適さない時期と言われてます。)
これから二週間、ダイエットには効果的です。
月の呼び名
十六夜以降の呼び名は、
「●待月」がしばらく続きます。
十六夜
立待月
居待月
寝待月
更待月
一夜一夜の月に名をつけるほど、月が身近に、愛でたい存在としてあったのでしょう。
そして数日後が下弦の月。
日本は古来「待ちの文化」を持っていたのも、わかりますね〜^^
太陽より月の文化なのかもしれないな、と思います。
昔の人は、満ちたり欠けたりするお月さまを眺めながら、
月に自らのこころをうつしてうたを詠んだり、
お月見をしたり、
ゆっくり昇るお月さまをゆったりと眺めながら、逢ふ人を待っていたのでしょうか・・・
待ち合わせに遅れたとき「月を観てたからいいよ」
ナ-ンテ言ってくれるジェントルマンが現代にもいらっしゃったら…素敵ですね♪
(/▽\)♪
下弦の月
満月から新月のに向かって欠けはじめる、ちょうど半分のところです。
続き
右半分が空いた半分です。
下弦の月は、夜中頃出て、正午頃に沈みます。
この時期は『意識の危機』と呼ばれ、
『自分の人生はこのままでよいのか』と自問自答することに。
心と体の葛藤が生じやすく、迷いやためらい、すれ違いも起きやすい時期。
心や魂について洞察を巡らせるのに適しています。
人間の本質を描いた本や映画から、勇気や感動が得られます。
誰かの助言やアドバイスにも、素直に耳を傾けると吉。
植物でいうと『収穫』に相当します。
また、地球からみて太陽と月の角度が90℃になる下弦時は・上弦時とともに、交通事故も多く、
兵庫県警交通部が全国の人身事故10年間のデータを分析した結果、下弦・上弦の前後に事故が多発し、
ピーク時には、新月・満月時よりも15〜20%も多かったそうです。
ちなみに、救急車・消防車の出動は、新月・満月時が多くなるといわれています。
おすすめは、
下弦月には『浄化』『解毒』の作用があるので、心と身体のデトックスを心がけて。掃除や庭の雑草取り、ヘアカットするにも適した時期。
手作りの化粧品などを作るのもおすすめです。
メンタルでは「調和」を心がけるとGood!
ひかえたほうがよいこと
短期の計画は、下弦の月のもとで実を結びますが、
新しいことを始めるのはタブーです。
植物の種まきや肥料を施すのには不向きな時期です。
種をまくのはやはり新月以降ですね。
また好きな人にアプローチするのもNGみたいです(;_;)
ヒーリングサロン オフィーリア
まずはお気軽にお問い合わせくださいね。
電話番号:090-1023-3593
所在地:大阪市住吉区長峡町2-1
営業時間:12:00〜18:00
(時間外応相談)