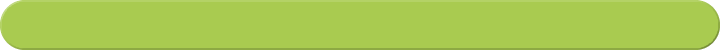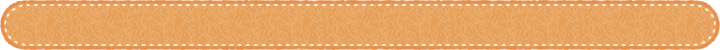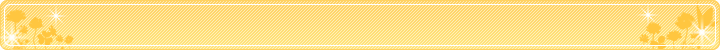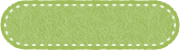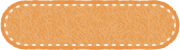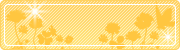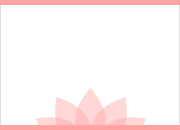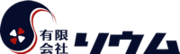- ホーム
- 笑顔のもと〔ほっこりコラム〕
- 暦について
笑顔のもと〔ほっこりコラム〕

74年前の3月13日は‥
2019/03/131945年3月13日深夜から翌日未明にかけて最初の大阪空襲が行なわれ、その後、6月1日、6月7日、6月15日、6月26日、7月10日、7月24日、8月14日に空襲が行なわれた。これらの空襲で一般市民 10,000人以上が死亡したと言われている。Wikipediaより
地下鉄による避難
3月13日、14日の大空襲は深夜に行われた。難波、心斎橋は猛火に包まれており、既に避難の術がなかった。通常、この時間には地下鉄は営業しておらず、駅の扉も開いていないはずであった。しかし、このときに心斎橋駅や本町駅、大国町駅に入り、電車に乗って避難したという体験者が複数存在する。Wikipediaより
節分によせて〜心の鬼退治
2019/02/03- 鬼は外。福は内。心に潜む鬼を退治して日々精進いたしましょう。
昔はどの家庭でも節分に「鬼は外。福は内」と豆まきをなさったことでしょう。鬼には5種類の鬼がいるそうです。赤鬼は欲深く何でも欲しがる鬼。青鬼は悪口ばかりを言って周りに毒吹く鬼。黒鬼は道理を知らずお先真っ暗な鬼。緑鬼は怠惰で怠け者の鬼。黄鬼は自分勝手で我儘な鬼。赤鬼、青鬼、黒鬼は特に厄介で、仏教では三毒煩悩と呼ばれる鬼です。この鬼たちは地獄にいるわけではありません。皆、人間の心に潜んでいる鬼です。心も身体と同じで放っておけば垢が溜まります。鬼はこの心の垢が大好物。風呂に入って体を洗うのと同じように、心も洗っておかなければ汚れてしまう。心の中に潜んでいる鬼は豆をまいたぐらいでは逃げてはくれません。日々洗心し心中の鬼を退治することが肝心です。貴方の心の中ではどの鬼が一番力を持っているのでしょうね。妙徳山 華厳寺住職
中秋の名月【十五夜】の由来
2017/10/03今年も大好きな十五夜がやってきます。
今年は10月4日です。
秋は、空が高く澄み渡り、月がひときわ明るく美しく見える時期。
一年でもっとも美しいとされるのが「中秋の名月」。
別名を「十五夜」「望月」とも言われます。
旧暦では、7〜9月が秋とされ、
7月:初秋
8月:仲秋
9月:晩秋
と呼んでいました。仲秋は8月全般の意味で、
「中秋」は秋のちょうど真ん中にある「8月15日」のこと。
「中秋の名月」とは、8月15日限定の満月を指します。
今年の中秋の名月(十五夜)は10月4日ですが、満月は6日。
月の周期は約29.5日なので、十五夜(旧暦)が必ず満月とは限りません^^
1〜2日のずれがあるのですね。
29.5×12か月で、太陰暦の1年は354日。太陽暦の1年は365日ですから、
ここでもずれが生じますし、数年経つと暦と季節がずれてしまうので、
3年に1度うるう月を設け、季節に合うよう調整します。
これが太陽太陰暦で、明治の改暦まで使っていました。
お正月を始め、日本の年中行事の多くが暦と季節感にずれがあるのは、
こうした理由からだそうですね。
十五夜では、観月祭を行う寺社仏閣が数多くあり、住吉大社でも太鼓橋の上で舞いや和歌などが奉納されます。
一般でも、月がひときわ明るく美しい中秋の名月を観賞する風習があります。日本古来のものかと思っていたのですが、もともとは中国の習わしです。
3000年余の歴史を持つ中国の伝統的な祭事「中秋節」に由来する風習だそうです。
三五夜(さんごや)という、天人が降りてくる日として、 瓜や果物、枝豆や鶏頭をささげ、 月を賞(め)でました。
これを日本に伝えたのは遣唐使だとされます。
奈良〜平安の時代にかけて、朝廷の貴人たちを中心に「月見」の宴が開かれるようになりました。
電灯などなかった時代、月のない夜はほんとうに真っ暗だったと思います。
だからこそ、明るい満月の光で夜を楽しむことは特別だったのでしょう。
貴族たちは、池の水や酒杯に映り込んだ「十五夜」の満月を愛でながら、詩歌を詠み、管弦で優美な月見の宴を楽しんだと言います。
月月に 月見る月は多けれど 月見る月は この月の月
作者は不詳ですが、これも宮中の女官たちによって歌われたと伝えられています。
「この月の月」は、そう「中秋の名月」を指します。
江戸時代になると、お月見の風習は庶民へと広がり、
優雅な遊びから収穫の喜びと感謝をささげる収穫祭の意味を持つようになりました。
お月見のころは、ちょうど秋の収穫時期に当たることから、十五夜の満月は豊かな実りの象徴として崇められ
家々ではお月さまが見える縁側や庭先に「月見台」を設け、
サト芋や団子、枝豆、ススキなど、秋の収穫物をお供えし、月を鑑賞しました。
地域によっては「芋名月」とも呼ばれています。
平安時代初期に書かれた日本最古の物語「竹取物語」。
ヒロインのかぐや姫が月に帰った日が、8月15日の「十五夜」でした。
その頃からとても美しい月だったのでしょう。
昔から続くお月見の楽しみ方を知りながら中秋の名月を愛でると、またひときわ美しい名月と出逢えるかも♪

七夕さん♪古来の棚機(たなばた)
2017/07/02ほっこり写真館にもアップした
住吉大社にご挨拶に行くと…
境内に笹の飾り付けがされていました☆
ああ七夕さんだなあと思いながら、短冊に願い事を♪
いえいえ、しておりません(;^_^A
涼しげな風情に、こころもち…暑さも忘れます。

そんな『七夕』、興味深い起源:「棚機」(たなばた)を知りました。
『棚機(たなばた)』とは
中国の『棚機(たなばた)』という古い禊ぎの行事。
乙女が着物を織って棚にそなえ、神様を迎えて秋の豊作を祈り、
人々のけがれをはらうというものでした。
選ばれた乙女は「棚機女(たなつばめ)」と呼ばれ、
川などの清い水辺にある機屋にこもって
神様のために心を込めて着物を織りました。
その時に使われていたのが「棚機(たなばた)」という織り機。
やがて仏教が伝わると、この行事はお盆を迎える準備として
7月7日の夜に行われるようになりました。
そういえば昔は旧暦なので、旧暦の七夕というと8月上旬になりますね。
現在「七夕」を「たなばた」と読んでいるのもこの『棚機』から来ているそうです。
節分の豆(豆知識)
2017/02/012月になりました。
2月のおついたちを迎え、これからの自分に必要な流れがやってきてるのを感じています。
節分が近いから余計にテンションが上がっているのかもしれません^^
節分は2月3日。3日に豆まきをして邪気を払い、翌日の立春を迎えます。
昔はこの「立春」だけでなく、季節の変わり目にあたる「立夏」「立秋」「立冬」。
その「節目」が、すべて節分とされていました。
一年の節目に当たる立春に重きを置かれはじめたのは、室町時代からだそう。
季節の変わり目には「鬼」が出てくるといわれ、
豆=魔滅 の音に通じることから「鬼は外、福は内」のかけ声で豆まきをするならわしがはじまったとか。
私は「鬼」を「邪気」「自分の元気を阻害するもの」に見立てて豆まきをします。
豆が撒けない環境の方も多いと思いますが、
窓をあけて、手のひらにいくつかの豆が入っていると見立て、豆撒きのポーズをとるだけでも、
鬼発散ができるとおもいます。
オニはどこにいるでしょうか。
外:自然界にもいるし、内:自分の中にもいるかもしれない。
魔と呼ばれるものもありますね。
自分を制限する思い込みや、新しい自分にはもういらない感情、
こわい形相をしたオニは、いろんな役を買って出て、私たちの成長を底上げしてくれてるかもしれない。
それはそうと、お寿司屋さんでは一年で一番の忙しさ、恵方巻。
今は全国に広がっていますが、もともとは関西が発祥の食文化、海苔屋さんの商戦だったとか。
私が20代の頃に、地方から出てこられた方が「節分にお寿司を食べるのは、大阪に出てきて知ったよ。」
と言われてました。
それを全国に広めたのが、コンビニエンスストアだと聞きました。
七福神にちなんで、かんぴょう、きゅうり…・・など、7種の具を入れて巻くと良いそうです。
魔除けも七色といわれますね。
厄のときは、長いものに巻かれろとも言われます。
7種の具材を巻いて、恵方を取って、味わいながら食べるのもいいですね。
古来より季節の変わり目に出てくるといわれてきた「鬼」。
豆まき=魔滅まき
その鬼はなにかを終わらせてくれるエネルギーなのかもしれません。

秋分の日【日想観】
2015/09/23ヒーリングサロン オフィーリア
まずはお気軽にお問い合わせくださいね。
電話番号:090-1023-3593
所在地:大阪市住吉区長峡町2-1
営業時間:12:00〜18:00
(時間外応相談)