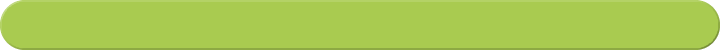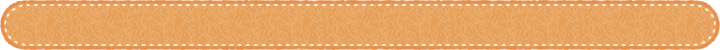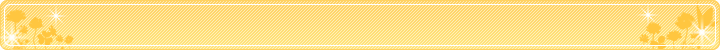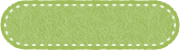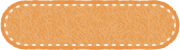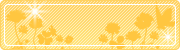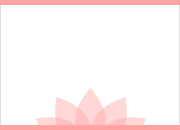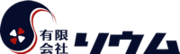- ホーム
- 笑顔のもと〔ほっこりコラム〕
- 暦について
- 秋分の日【日想観】
秋分の日【日想観】
2015/09/239月から、月のことを書きはじめました
仲秋の名月も素敵な習わしですが、
もうひとつ外せないポイントが〔秋分〕です。
彼岸の中日が秋分の日です。
ご存じのように、昼と夜の長さが同じ、太陽が真東から昇り、真西に沈みます。
お墓まいりに行かれた方も多いと思いますが
まだ行けてないのですが、母方のお墓が四天王寺さんにあります。
四天王寺では春分の日と秋分の日に
誰もが参列できる「日想観」(じっそうかん)という法要があります。
とても大切な意味が込められた行事なので、
紹介したいと思います。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
極楽浄土へ往生願い西に夕日を拝む 日想観
(略)
春分と秋分の日、大鳥居と門の真ん中を通って夕日が沈む。
極楽門の下で僧侶10人が念仏を唱え、参拝者が夕日に手を合わせる。
(略)
平安時代から室町時代にかけて盛んだった仏教の信仰はいつも頃からか廃れたが
近年大阪や京都でこの伝統行事を復活する寺が相次いでいる。
四天王寺には、8世紀の終わり頃に、空海が西門で日想観をした記録が最古で
親鸞や法然、法王や天皇まで訪れ
また和歌山の熊野詣が盛んだった頃は
京の都を出発した日の夕方にこの一帯に到着すると夕日を拝める…
と流行した。
前の住職さんいわく…
今でこそ、この一帯はビルマンションが立っていますが、
住吉大社付近と同様、かつてはすぐ西側まで大阪湾で
海の向こうに見える六甲山と淡路島の間に沈む夕日が拝めた。
この一帯は「夕陽丘」の地名が示す通り、夕日の名所で
平安から室町にかけてパワースポットだった。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ずっと継がれてきたのでは なかったのに驚きました!
復活させたのは、なんと2002年。。
150年ほどの間、廃れてしまった理由は…
明治初期の神仏分離令や、大阪空襲(1945年)でお寺が焼けたりで
じょじょに廃れた。
↓
21世紀になって復活したりゆうは・・?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
僧侶のKさん
「極楽浄土にいるご先祖を思うだけでなく、昇っては沈む太陽に生命の循環を感じ、
生かされている喜びを実感してほしい」
宗教学者のYさん
「日本人は落日の彼方に極楽浄土を思い浮かべ夕日を拝むことで心が洗われ、
自然に包まれて生きることの大切さを実感してきた。」
そんな心が日本人の心の中にDNAとして残っている。
「夕焼け小焼け」の歌詞に、自然との共生を説く仏教の教えや無情観を見いだし、
夕日を拝む大切さを唱える。
時代的に
高齢化社会、阪神大震災や東日本大震災に見舞われた今、どう生きたらいいのか…?
また企業戦士は夕日を見る余裕がないかもしれない。
夕日を拝むことで自然の包容力を感じ、
心を癒してほしい。
そんな願いからの復活。。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
引用終わり。
たしかに最寄駅は、地下鉄「四天王寺前夕陽ヶ丘」。
昔、なぜこんなところが「夕陽ヶ丘」なの? って思ってたけど、納得!
地元のすばらしさを再認識し
こんな、こころを大切にする行事をこれからも復活させていってほしい。
じょじょに、日本人の精神性の息吹きがよみがえるのを願って…
先行きのみえない時代、余裕のない心をもつ人も少なくなく(特に都心では)
殺伐としたこころを救うのは日本人の心のDNA。
忙しいかもしれないけど
ふと立ち止まり、沈む夕日や、昇る月をみる。
そこにいのちの循環を感じ
生かされていることに感謝のできる自分で いつもいたい。
いのちの循環といえば やはりお彼岸。
いのちを繋いでくださったご先祖さまに墓参りし手を合わせるお彼岸の恒例にもやはり通じる。
次回は、来年三月のお彼岸。
半年後、生きてられない人もいるだろうし、仕事で行けないかもしれないし
曇りや雨かもしれない。
いつも夕日を拝めるとは限らない。
だからこそ、今を大切に、輝かせていたい
晴れて夕日を拝めたほうが、みんなが喜ぶ。幸せを祈れる人が増える。
どうか晴れますように
そして、日本人の心も明るい光で満たされますように・・・
感謝と祈りをこめて・・・
今回私は、日想観(じっそうかん)で、真西の大鳥居に沈む夕日をみることはできませんが、
夕日や月を見ながら、手を合わせる気持ちを忘れずにいたいと思います。
ヒーリングサロン オフィーリア
まずはお気軽にお問い合わせくださいね。
電話番号:090-1023-3593
所在地:大阪市住吉区長峡町2-1
営業時間:12:00〜18:00
(時間外応相談)