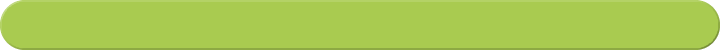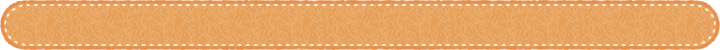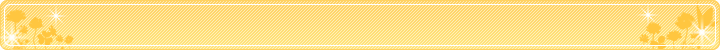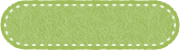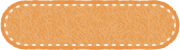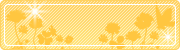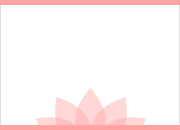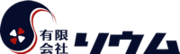- ホーム
- 笑顔のもと〔ほっこりコラム〕
- 季節の過ごしかた
笑顔のもと〔ほっこりコラム〕

梅雨どきの心の古傷
2023/06/02梅雨は日本の四季で一番憂うつな時期かもしれません。

特に、皮膚にまとわりつくような湿度の日は不快指数も高いですし
やる気が出ない··など
気持ちが下がり気味になったり、
頭が痛い、肩こり、だるい…
などといった症状があったりする方も少なくありません。
気圧や湿度の変化で出てくるのですが、
梅雨には両方あるため、より体調を崩してしまいやすいのですね。
つかみどころのない気だるさに「気のせい?」と思ってしまいがちですが、
それもある意味正解(^^;
「梅雨の気(象)のせい」でもあるのですね^^
気候に敏感な方はご自分に ケア心 で向きあってあげてください。

また、梅雨は古傷が出てくる時期でもあります。
過去にケガを負った箇所に痛みが出たりすることが多いのです。
「古傷が痛むから雨が降る」
など
天気予報よりリアルに予測する方もいらっしゃるかもしれません^^
そもそも古傷とは、どんなものでしょうか?
辞書では
「過去に怪我をしたところ」、「古い傷のあと」
と解説されています。
交通事故やスポーツで痛めたり、手術の傷あとなどで、筋肉に傷を負っている状態を言います。
ではなぜ再び痛み出すことになるのでしょう···
ひとつは天候です。
気圧が低くなると、痛みを感じさせる物質が体から分泌され(ヒスタミン)、古傷などの痛みにつながる
それが『天気痛』と呼ばれるのですね。
次に
ほとんどの怪我で負った傷というのは、
皮膚の表面上は完治したように見えても、実は皮下や筋肉の組織には傷が残っていることが多い
(>_<")
古傷は表面でなく内側で起こっているのです。。
この肉体の「古傷」。
過去に傷ついたこと・その傷あとなど、
心にも通じるものが あるのではないでしょうか
解決したと思っていたのに···
悶々しだす・イライラする・心がざわついて落ち着かない···
などといった状態。
・あのときの感情が上がってくる…
・やっぱり、まだアカン(>_<)
… など
こころの古傷が、湿気にうずいて、顕在意識に伝えられてきているのです。
ご自分でできるケアとしては、深呼吸と温めです。
梅雨時は、呼吸で取り込む酸素の量が少なく呼吸も浅くなりがちなので、
いつもより呼吸に意識を向け、深めの呼吸を心がけるといいですね。
入浴では、ぬるめの湯船にゆっくり浸かり、
余裕があれば '冷えや心身の痛みがほぐれ流れるイメージ'
でいるとさらにいいです♪
『梅雨明けまではひじ・ひざを出すな』と昔からいわれますが、
体を冷やさないようにするのも大事ですね。

セラピー的には、傷が浮上してきているときは
痛みを解消するチャンスでもあります。
自分発見!こころみつめセラピー がおすすめです。
ケアではないですが、涙活(るいかつ)と呼ばれるものがあります。
涙活とは…
感動できる映画を見るなどして能動的に涙を流すことで、心のデトックスやストレスの軽減をはかる活動
涙には、一般的に脳内から分泌されるストレス物質が含まれ、
涙を流すことでそれらが排出されます。
中でも「情感」や「感動」の涙が、同じ涙でも抜群です。
心の深くが呼び覚まされるので、癒しも同時に起きるのでしょう。
ご自宅のインターネットやDVDでなど観賞したり、映画をみたり
朗読を聞く涙活イベントに参加されてもいいですね。
雨のように涙を流していく…ちょっと違った時空を過ごしてみるのもまた乙です。
梅雨は、植物の生長や実りの秋を迎える大切な準備の時期でもあります。
ちょっとやさしい気持ちで楽しみを見つけながら
「一年の計はおせちにあり」実りのあるよい一年を
2023/01/01「一年の計は元旦にあり」
という諺を、聞いたことがありますね。
ところで
「一年の計はおせちにあり」
は、聞いたことはおありでしょうか☆
おせち料理を頂かれてる方も多いと思いますが
そもそも・・
三が日におせち料理のごちそうをいただくのは、なぜだかご存じですか^^
・お正月はお店はどこも休みだから保存できるように…
もありますが、
実はおせち料理も
「予祝」(よしゅく) です。
あらかじめ盛大に祝うことで、
そう☆
引き寄せです。
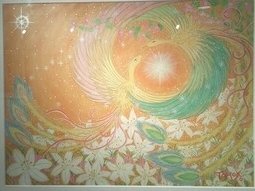
毎年のおせち料理をいただくだけで、
実りの多い、よい一年を引き寄せてるのです。
日本人って予祝を好んで行っていたのですね〜(*^^*)
今は、形骸化してしまってますが、
なぜ、お正月におせち料理をいただくのか、
意味を知ることで、
また違った頂き方になるればいいですね(*^^*)
幸先をイメージされながら、お好きなお料理をいただかれてください(^-^)
すべての人々が、一日も早く、安心して過ごせる日が訪れますように願っています。
本年もどうぞよろしくお願いします。
事始めの日~暦からメッセージを頂いてみる。
2022/12/13色んなことがあったと思います。私も色々ありましたが(^^;
好ましい出来事ばかりでなく、どうしても後ろ向きな思いになってしまったことも
そうわかってはいても感情に走ってしまったり、
あんなこともあった、こんなこともあった・・・
でもせっかくこの時期なので、思い出すだけにとどまらず(^-^;
◇じゃあ来年はこうしよう!
◇「感謝」に帰してみる
が、できたらいいなと思います。
今日、12月13日は暦からのメッセージがいただける日です☆
(かつては旧暦の12月13日でしたが、現在は新暦の12月13日がその日に当たります。)
・一年間大切に使って古くなったもの
・汚れが溜まってきた場所
・マンネリ化してきた気持ちなどの一新
物も気持ちもクリアにし、すっきりと心地よく新年を迎えるための
ピッタリのタイミングなのでしょう。
具体的に「正月事始め」に始めると良いとされているのは、かつては、
「煤払い(すすはらい)」や「松迎え(まつむかえ)」というならわしでしたが、
ほっこりコラム版の「事始め」
---
~少し瞑想的に~
動物も草木も眠るこの時期、
一見すべての動きが止まってしまったかのようですが、
草木や地面の内側では、春に備えてじっとエネルギーを温存します。
人間も、自分らしい人生を巡らせるために、エネルギー(気)をしっかり蓄える時期で
自分の本質とつながるのに適しています。
ご自分の内側から湧いてくる価値観や思いを大切に
なぜか、ふと興味が湧くもの。
自分に向いているかわからないのに、ずっと気になって心から離れないもの。
それらはもしかすると自分らしく生きるための導きとなってくれるもの…
かもしれません。
そういった直感を大事にされ、本当に大切にしたい価値観を
心静かに感じてみましょう。

たとえば…
人と人とを繋げることをしたい。
若いとき興味があったことをもう一度やってみたい。
女性の孤独を助けること、なにかできないかな…
手放し、断捨離かな
なにか具体策でひらめくものがあるかもしれないですね。
師走をただ忙しく過ごして年越しするよりも、毎年新しい自分に出会うための準備が、この年末にできたら素敵です。
年越しまでは、あと2週間少しありますから、十分大丈夫^^
世間で幸せと言われる生き方をしても、他の誰かの生き方を真似してみても、、
ご自分が本当に大切にしたい価値観と違っていたら、
早かれ遅かれ、どこか満たされない感が出てきて、行き詰まってしまうんですよね。
内側と深く繋がり、湧き上がり、大切に大切に集めたひらめきの種。
それに沿ったものならきっと大丈夫。
種はどれだけ沢山あってもOK ですよ。
新しい自分と出会うための準備。
でも、新しい自分というのは、何者かに変身した自分ではなく、
内側からくる(湧きでる・溢れる・思い出す)本来の自分なのではと
思うのです。

冬、なぜか気分が沈んでしまうのは…
2022/01/14
- 眠気が強くなる
- 食欲が旺盛になる
- 気分が落ち込みやすくなる
さらに症状が悪化すると、うつ病や不眠症といった症状を発症してしまうこともあるので、
軽視できません。
ではこの時期、気が滅入らないようにするには…
冬季うつ病の原因は日照量の減少なので
朝起きたらカーテンを開けて太陽の光を浴びたり、
できるだけお昼間のうちに太陽の光を浴びておくとよいですね。
曇りの日でも、空をみるだけでもちがってきます。
新年にご自分の神性とつながってみる
2022/01/01明けましておめでとうございます(*^-^*)
年末から寒気の影響で朝もぐっと冷え込みましたが、
大阪では日差しもみられ、すがすがしい気持ちで新年を迎えることができました。

お正月は一年で一番、手を合わせる機会が多いかもしれません。
新しい年を迎えれたことへの感謝と、今年一年の抱負と安寧を祈ります。
皆様はお詣り(初詣)に、お出かけになりましたか。
混雑した神社仏閣では、私は拝殿の後続が気になって
ゆっくり心静かに手を合わせることが難しく、詣った気がしないことが多いのですが(^-^;
人の少ない早朝や、人気(ひとけ)の少ない寺社が良いようですね☆
ステイホーム派の方は、ご自宅の神棚やお仏壇にお詣りされるだけで
十分ですよ。
祀られている神さまと静かな心で向き合い、清らかな心で手を合わせると
ご自分の中にある神性とつながることができます。
ご自分の神性に灯(光)が灯ると・・・
ご自分を尊重する感覚が生まれ、
思いや決断、選択に自信がもてるようになります。
お一人、おひとりと、セッションしていると、
その方にしかない素晴らしいもの…がおありで、
それがどなたにも在るのですね☆
ただ、その光に曇りがかかっているだけ。

新しい年に、ご自分の神性を思い出す。
そんな年明けでありますように。
なにかひとつでも気づけるといいですね。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

「冷え」を感じてみる。
2019/01/10屋外や暖房のない部屋に長時間いたり、雨や雪に降られてしまったりすると、体がすっかり冷えきってしまうことがありますよね。、
感じています。
またそれは次のほっこりコラムで♪(^^)
と書きました。
〜今日はその続きです。
どろどろしてた、してる、かもしれない、でも自分の’原作’には違いない、確かな思いの塊。
冷えはメンタルにも大敵、気分の落ち込みも。
2018/12/11ここ数日で急に寒くなりましたね。
こうも急に寒いと、カラダの寒さ順応センサーがなかなか作動せず
寒さに馴れようとゆっくり適応中です(^^;
私は大変寒がりなのですが、手足がよく冷え、
極寒期の底冷えは、体の芯まで冷え込んで厳しいもの。
冷えは、女子によくある痛みや不快感、不調の原因になることが知られています。
肩こりや腰痛、頭痛、足のむくみ、生理不順…など辛いものですね。
体が冷えると、血流が悪くなって全身に酸素を送れない、栄養を与えられない‥そして色んな不調をきたしてしまうのですね。
リンパの流れも悪いので、老廃物の排出もスムーズにいかないでしょう‥。
しかしこの冷え、体だけでなく心にも不調をきたすと言われています。
・なんだか落ち込む
・やる気がでない
・気持ちがもやもやする
・イライラを感じやすい
そういったメンタルにもなりやすく、
『鬱なのかもしれない・・・』
と思ってしまう方も少なくありません。
冷えは、ただ寒がり、ではなく、すべての不調の原因になりえます。
やる気がでない、落ち込みやすくて、、なども
冷えを解消していくことで、楽になり、
こころが軽くなって、気持ちもしだいにほっこりあたたかくなる‥。
そんなことも多いのです。
あと、冷えているとうつ傾向になりやすい理由のひとつとして、脳内の分泌ホルモンの働き(の衰え)も挙げられます。
冷えているとホルモンに影響し、“快楽ホルモン”のドーパミンや“癒しホルモン”のセロトニンの分泌が衰え、やる気がなくなったり落ち込みやすくなり、うつ傾向に。と言われています。
思ったより、こころにダメージが及ぶ、冷え。
からだをゆるめ、あたため、
〈冷え〉を溶いてあげてくださいね。
私の感覚では、冷えは、その人の、けっこう深い根っこのところにあると
感じています。
またそれは次のほっこりコラムで♪(^^)
今日から18日間 秋の土用です
2017/10/20本日、10月20日(金)14:07
〜
11月7日(月)14:38に迎える
立冬直前まで です。
暦は立冬でも、11月7日といえば秋真っ盛り(^^♪紅葉狩りに最適、様々な行楽が楽しめます。
日没時は、この季節特有の “つるべ落とし” 。あっという間に夕闇に包まれます。
季節の「気」が冬へと変わりだしたので、秋に戻ったり冬に進んだりしながら、徐々に冬の気が勝っていきます。
土用のかかりに季節はずれの台風が接近しますが、台風は熱帯低気圧が発達したもの。冬は寒波。
寒い台風だなぁと思って過ごしていますが、2つの気がうずめくのも土用の特徴ですね。
冬になると気温の低下だけでなく「冷え」が入ってきます。お肌の乾燥もはじまります。
カラダが、そして心も冬モードになろうとゆっくり調整をはじめます。
旧暦の秋(8月の立秋)から、今日までにたまったストレスや疲労物質を自動浄化しようとするのですね。
そのひとつが 秋バテ 。夏バテだけでなく「秋バテ」もあります。中でも「気温差不調」は何ともしんどいですね。
気温差不調とは、文字通り気温差によるカラダの不調のこと。
急激な気温の上がり下がりにカラダもどう対応すればいいのか…特に寒さ対応の働きが急にはできないもの。
頭が痛い、首肩まわりが張る、体がだるい、といった不調が出てきます。
不調にとどまらず、老廃物や邪気の発散パワーが高まって、セキや鼻水・熱などの風邪をひいたり、
毒素を出そうとして、食べ過ぎてしまったりすることもあるかもしれません。
土用後半、冬の気が強くなると、寒さで血液の流れが悪くなって、お肌も乾燥・肌荒れしやすくなるようです。
肌荒れの吹き出物もなにかを出そうとする働きなのでしょう。
メンタル的には、秋:悲しみや孤独 といった感情から
冬:驚きや恐怖へと、移ります。
たとえば…「あぁびっくりした〜」 といった” 驚き仰天 ” な反応、驚きあまった恐怖などが もよおされやすく…
気が乱れ慌てて混乱してしまいます。軽いパニックに陥らないよう気をつけたいものですね。
あと、「SAD」という この季節特有の「季節性の感情障害」があります。
冬場は日照時間も短くなり天気も悪くなりやすい。そんな天候に左右されて気分障害が起きるのです。
気分が落ち込む、イライラする、物事を楽しめず人と関わりたくなくなる…などの症状ですが、
いろんな気がどよめく土用も、SADをより感じやすくなるかもしれません。
そんなときは、晴れの日の日中、お日さまの光に当たってみるのがおすすめです。
綺麗な紅葉を観に、思い切って外へ出たり、誰かと話したり、おいしいものを食べたり…(*^-^*)と、心にも栄養を与えてあげましょう。
そして何より、日ごろ自分を労わってあげることが大切♪
常に心と体のバランスが取れた生活を心がけていれば大丈夫!
自分ではちょっと…煮詰まってきそう・・・といった方は、どうぞ私に話しにいらしてください。
ちょっとエネルギーを使う土用を乗り切ると、秋本番!晩秋になります。
これまでがんばってきたこと・取り組んできたことを醸造させたり、実らせたりしながら、ご自分の器を大きくし、師走を迎えたいですね…☆

夏の土用がはじまりました。
2017/07/19今ー年の夏土用は、
本日、7月19日(水)20:54
〜
8月7日(月)16:42に迎える
立秋直前まで です。
暦は立秋でも、8月7日といえば暑さのピーク。
でも、確実に日は短くなり、秋の風物詩である赤とんぼがみられるのもこの頃からですね。
温暖化の影響でうだるような暑さが続き、日によって気温も上下はしますが
季節の「気」が秋へと変わりだしたので、8月7日を境に、ゆるゆると気温が頂上から下がっていきます。
季節が秋になり、気温が下がり始めると
カラダと心も秋モードになろうと調整をはじめます。
旧暦の夏(5月の立夏)から、今日までにたまった
ストレスや疲労物質を自動浄化しようとするのですね。
そのひとつが 夏風邪 ですね。
老廃物や邪気の発散パワーが高まり、異常な汗をかいたり、
毒素を出そうとして、食べ過ぎてしまったりすることもあるかもしれません。
エアコン部屋と外気の行き来でクラッときたり、自律神経のバランスも気になります。
メンタル的には、春:笑いや喜びの感情 から
秋:悲しみや孤独 といった感情へと、移ります。
ハラハラと落ちる葉をみて、さみしくなってしまうのも秋ならでは。
大きな括りでは
陽 → 陰 へと 大きく変わっていっています。
太陽まぶしく日も長い季節から、やさしい日射しにうつっていく日の短い季節へ 移ります。
まだまだ落葉はみられないし、ハラハラ泣くのは早いですが(;^_^A
5月初旬からがんばってきた心のハリキリがあったら、この土用中にちょっと振り返り、一休みしてもいいですね。
でも、考え過ぎには気をつけてくださいね。
土用期間中は、メンタル的は結構、思い煩いやすく、クヨクヨしやすくなったりします。
そんなときは、昨日までとは違った、秋の「気」の風を感じてみましょうか(^^)
初秋へとうつる風に吹かれながら流していけば大丈夫〜(^-^*)
あと、脾臓(ひぞう)が働き過ぎたり、<食べ過ぎ>
働かなさすぎたり、<食欲不振>
するので、気をつけてくださいね。
***
こちらもご覧になってくださいね。
この土用の過ごし方のいい感じで、秋の迎えがちがってきます!
食欲の秋、収穫の秋、
人間的にも実りの秋 となるように…
ご一緒にがんばりましょう(*^o^)/\(^-^*)
季節の変わり目「春土用」の過ごしかた(メンタル)
2017/04/17今日は暖かい雨が降っています。
今年は暖かくなるのが遅く、桜も例年よりゆっくり楽しめましたね。
暦(こよみ)上の「春」は・・・今日で終わりました。
そもそも土用とは、昔ながらの日本人の生活の智恵「雑節」のひとつで、季節の変わり目を指します。
立春・立夏・立秋・立冬直前の約18日間で、年4回あります。
数日前の急な気温上昇など夏を思わせる暑さもあり、エネルギーがアップしています。
しかし季節の変わり目は、何かと混沌としてイライラ・フツフツしたり、心がもやもやと乱れがちになります。
春の心身から夏の心身へ移るために、
たまったストレスや疲労感を…心身が自動浄化しようとしている…
そう考えるといいですね〜
浄化作用(デトックス)です。
どの土用も共通している乗り切り方のオススメは、モヤモヤをスッキリさせる心身の浄化、デトックスなのです。
春土用である今は、
いらいらの解消、発散できなかった不満、怒り系の感情の解き放ち
抑え込んだ感情の癒しもおすすめです。
溜まったままでいると、夏以降、それらがくすぶったまま高ぶってしまい、
highになりすぎたり(過度な気の高ぶり)、逆に不安や気力減退、うつ傾向におちいりやすくなります。
五月病といわれるゆえんもそうですね。。
もしもプチうつになっても…カラダも心もゆっくり休めて
いま、新しい季節への調整をしてるんだ(´▽`;)ゞと
流していきましょう。
- ◆ひかえたほうがよいこと
・判断を間違えやすい時なので、大事な決断は保留にしましょう。
(2つの季節の気がドヨメクので、自然の影響を受ける人間の気も、揺さぶりが起きやすいのですね)
・新しいことを始めることもNG、立夏5月5日まで待ちましょう!
(開店・開業、就職・転職、結婚・結納、地鎮祭・新居の購入・増改築・引越)
・土に関することがNGなので、人生の土台に触れること、
気分転換にガーデニングも、残念ながらNGです。
穴をあけることもダメなので、ピアスの穴あけも控えてくださいね。
- ◇その他オススメ
・目が疲れやすいので、新緑を見たりしましょう。
・ゆっくり過ごせること(温泉、半身浴、瞑想)
・少食、断食(カラダのデトックスの一貫)・断捨離、大掃除(除年末大掃除でやりそびれた所)、整理整頓
今日から過ごす土用も、ゴールデンウィークを経、5月5日に夏の始まり:立夏を迎えます。
「夏」の計画を「立てる」のもいいですね。

春はプチうつ、そう感じたら…
2017/04/13桜も散り始め、散った枝から新緑が芽吹きだしました。
学校や職場も新年度がはじまり、新しい環境で過ごされている人も多くいらっしゃるでしょう。

実はこの4月、5月、そして6月まで・・・
一年のうちでも、最も心身の不調を感じやすい時期。
こんなに自然は伸びやかで、草木は芽吹き花は咲き〜(^^♪
なのにどうして自分はこんなにうつうつしてんだろ…と、ギャップについていけなかたりします。
その理由はここにあります〜
- 人間の体は春から夏にかけて活動的になって、秋から冬にかけて沈静する。
- 冬から春への変わり目が、沈静から目を覚まし、さぁ活動!となるタイミング。
- 冬から一転!光まぶしい春へと、カラダさんはバッチリついていくでしょうか…(汗)
もちろんカラダさんは、季節の変わり目の変化に適応しようとがんばります。
でもがんばりすぎて、余分な気を消耗してしまうこともあって…
これがバランスを崩すもとになっているのですね。
このように春は、陽気の高まりに心身が対応できず、プチうつになりやすいことが
東洋医学の観点からわかっています。
また40代を過ぎると、季節の変化への適用力、残念ながら低下しています。
・顔がほてったり・些細なことでイラッときたり・頭が冴えすぎてよく眠れない
といった不調が出てきます。
特に4月は、まだ3月を引きずった真冬並みの寒さもあれば、5月下旬の蒸し暑さもある。
一日の中でも気温差も大きく、自然環境に身体が順応しづらいですね。
今や日本人の1/4が発症している花粉症。不快に過ごしている方も少なくありません。
この吹き荒れる「風」も、体に害を及ぼす原因のひとつになるようです。
精神的には、学校や職場の環境が変わるので、ストレスを感じやすい時期であります。
そのストレスが「なんかいつもしんどいなぁ」と慢性的なってしまうと、
いわゆる「五月病」そして「六月病」となり、倦怠感、眠りが浅い、など様々な症状が現れます。
実は男性の身体は、それほど季節の変化に影響を受けないことがわかっています。(AEAJ機関紙より)
女性は反対に大きく影響を受け、その原因は女性ホルモンの働き。
成熟期の女性の身体はひと月に2回ホルモン分泌が変化し、体温が1度近く変動。
妊娠、出産、閉経とホルモン分泌が急に変わる時期ももっています。
身体がとてもデリケートにできているので、外部からの影響を受けやすいのだそう。
女性の活躍と言われ久しい昨今ではありますが、実は女性は繊細な面をもっていることを
忘れないでいてあげてください。
季節の変わり目、すこやかに過ごすには、ちょっぴり自分にやさしく、気を配ってあげることがたいせつ。
私からのメッセージ♪
春はみんながんばってます。この時期を乗り切るだけで、体もがんばってます。
こなすだけでいい。

寒土用後半〜立春の過ごし方*後編(メンタル)*
2017/01/231月5日に入った「寒」も後半になりました。
各地に寒気が流れ込み、大雪に見舞われる地域も出ています。
大阪でも急に時雨れては止み、時に晴れ間が差したりする日もあり
これも季節の気が変わっていく土用らしさかなと思います。
古来より人は、季節など自然の影響を受けながら体(内臓)を整え、自然のリズムに順応してきました。
特に東洋医学では、季節によって出やすい体調不良や内臓の不具合、精神症状があるといわれ
このコラムでは、季節や季節の変わり目に感じやすい感情やそのテーマのついて書きます。
季節で担当する臓器と、その臓器と関係している感情がある。という説を聞いたことはありませんか?
今回の土用は「冬」から「春」への変わり目です。
冬を担当する臓器は「腎臓」、関係している感情は「恐れ」「驚き」です。
恐れる、驚く、といった感情が強すぎると、腎臓を傷つけ、精神が不安定になります。
原因のわからない不安感や恐れも含まれます。言いようのない不安感、大丈夫でしたか。
一方、春を担当する臓器は「肝臓」、関係している感情は「怒り」「苛立ち」です。
季節 | 臓器 | 感情 | エネルギー |
冬 | 腎臓 | 恐れ、驚き | 内へ向かう、保守 |
春 | 肝臓 | 怒り、苛立ち | 外へ向かう、奮起 |
土用(冬) | 脾臓 | 不安、動揺 | 浄化、調整 |
新しい季節へ向かう恐れと、早く馴染まなくては、といういらだち、
この2つのココロの間を揺れ動く「不安感」が反映している冬の土用。
冬の臓器、腎臓に関係する感情ケアが充分でないと、次の季節:春(肝臓)の季節をスッキリ迎えられません(>_<)
ご自分の中の恐れや恐怖、、土用期間中に思い切ってフィードバックしてみるのも手。
この冬、びっくりし過ぎて傷ついてしまったハートや感情、溜まったままになってませんか。濁っていませんか。
腎臓は尿を排出してくれますね。不要なモノを綺麗にし体外へ排出します。
腎臓のように、ご自分のココロも…
「出す」「水に流す」「手放す」という働きかけがよい流れを生みます。
実際に要らなくなったモノを捨ててもいいですね。
要らないものを棚卸しして、これまでのご自分を整理できている人は、恐れ、不安、そして焦りとも無縁で
伸びやかに枝を広げる木のように、すがすがしい“春”を迎えることができます。
土用は脾臓ががんばってくれてるので、不安だよ〜動揺してるよ〜と感じながら、手放しを促してくれてるのかもしれませんね。
2月4日から、いよいよ「立春」。その前日が節分ですね!
あ〜(-_-;)なんだかんだ言いながら時が経ってしまって、冬の感情ストレスが抜けきっていない私が居たとしたら…
はい!セラピーに♪も、もちろんOKですが、「節分」パワーにあやかってみましょ☆
そう、アノ「鬼は外〜!」のオニが、その役目を引き受けてくれます★
ご自分の中の恐れ、恐怖、心配、不安・・・オニさんをそれに見立てて、ご自分のために豆まきをしてね。
オニを退散できたら、ココロもすっきり♪
大吉な春を迎えることができるでしょう。

寒中の土用〜立春の過ごし方*後編(ボディ)*
2017/01/15
一年で一番寒い時でもありますが、体は少しずつ春への準備を始めています。
春への移行調整で、鼻水が出たり、秋から冬にかけて体感がなかった「汗」を感じることが増えたり
風邪やインフルエンザがはやるのもちょうどこの季節です。
胃がわるいときは、胃に「入れない」ことが養生。
寒から立春の過ごし方*前編*
2017/01/10トータルでみると約1カ月が「寒」なのですね。
いずれにしろ厳しい寒さはホント身体に堪えるものですね。((T_T))
寒仕込み、寒中見舞い、寒稽古、寒肥え、寒中水泳魚などは、この時期になります。
古来日本人は、この寒気を自然の恵みとして利用し様々な食品を作ってきました。
味噌や日本酒、醤油などの寒仕込み
寒風にさらして作る凍り豆腐や寒天、野菜や魚や蕎麦などの寒干し・・・
今では温度湿度を操って作ることも可能ですが、自然に寄り添って作るものは美味しさとエネルギーがきっと違って美味しさもひときわ(〃∇〃)
この時期は「寒」のエネルギーをにあやかり自分自身を仕込んでいく、来る春にそなえて自分自身を寒仕込みしていく…
「ありたい・なりたい私」に向かって…☆
といったことに適しているのかも☆しれません。
「仕込む」というのは…
技能や芸などが身につくよう,訓練・指導する。準備して整えておく。
などの意味があります。
厳しい行、仕事の技能や芸ごと…
心の面では、ものの考え方や捉え方、心がけ…
身体のリリースや、からだづくり…体質改善にも
この時期は、自分の根っこの「定着力」が強くなっています。
ありたい自分を設定して、習慣化。
根っこパワーが後押ししてくれます(^-^)
そのチカラは、一年の中で最も強いでしょう。
年が明け、どんな一年にしたい!と思いましたか?
さあ今はじめてみましょう(*^▽^)/★*☆♪
・いつも「ありがとう」の気持ちでいよう♪
・控えたかったアルコールや甘いもの、摂らなくても満足な胃腸に!
・猫背をリリースして、正しい姿勢を筋肉におぼえこませる
など、なんでもいいですね(*^_^)
オフィーリアのおすすめ
よい習慣☆貴女のペースで寒仕込み♪
この寒中は「冬土用」も含まれます。
土用は夏だけでなく各季節ごとにあり、季節の変わり目でバランスを崩しやすいときでもあります。
このページで書こうと思ってましたが、次コラムで、冬の土用の過ごし方について綴ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
新たなスタートを切る1年の節目《冬至》
2016/12/17お日さまの光がやさしい師走
やさしさゆえにどこか控え目で…勢い旺盛な冬将軍を立てているよう。
雪を想わせる冷たい風が頬に当たると身がキュッとなり、日の入りも早く即夕闇。
師走の気ぜわしさに拍車がかかるやん…(-_-;)毎年そう感じながら過ごしていますが、
今年も1年のうちで最も昼が短い「冬至」がもうすぐやってきます。
2016年、冬至を迎えるのは12月21日(水)日本時間で19:44
冬至は24節季のひとつで、そのエネルギーは寒の入りと言われる「小寒」1月6日まで続きます。
冬至の風物詩では、銭湯のゆず湯に浸かったりナンキンを食べたり・・などがポピュラーですね。
陰陽五行説では、陰が極まり陽に戻る始まりの日。弱まっていた太陽のチカラがこの日を境に復活し勢いを増していくと言われます。
ここから新たなスタートを切る1年の節目なのですね。
たとえ悪いことが続いても新たな幸運を呼び込むことができる。という意味から一陽来復とも呼ばれています☆
「不運が続いた後、幸運に向かう」「運気が上向く」という意味合いがあります。
なんだか救われるタイミング!私は皆がおめでたい元旦、豆まきをする節分よりも「冬至」の方が改まる感覚と期待感☆をもっています^^「太陽のお誕生日」とも言われうきうきします♪♪
冬至は「冬」に「至る」と書きますが、そもそも「冬」の語源は…
○寒々とした冷たさの「冷ゆ(ひゆ)」
○寒さで身体を奮わせることの「震う(ふるう)」
○すべての生命が春に向けて力を蓄えていく「殖ゆ(ふゆ)」
そして
○増殖し繁栄していく願いが込められた「増ゆ(ふゆ)」
があります。
言霊としては、日本書記に書かれている「恩頼(みたまのふゆ)」と深い関わりもあります。
「みたまのふゆ」とは、「神様の恵みにより生きる力をいただく」という意味です。
前出の冬の語源の1つ、”増ゆ”は、「冬から春に向けて、生きとし生けるものすべてが増殖し繁栄していくように」という願いが込められています。
そんな語源や言霊に思いを馳せて、ありがたく冬を過ごすのも、素敵ですね(*^_^*)
"冬"に増殖し繁栄していくのは・・・
『根』です。
冬は根がアクティブになるとき。
この時期、どれだけ根が張れるかで生命力が違ってきます。
庭木に『寒肥え』(かんごえ)をするのも極寒のころですね。
冬はすべてのものに感謝しながら、力を蓄える充電期間なのです。
土の中でじっと春を待つ生き物たちのように、いったん身を縮めてエネルギーを蓄えていく。
やり残したこと、後悔することがあっても、過去をいっさい引きずらない、未来は明るいもの☆と確信する
冬至エネルギーは、そんな決意の大きな力となってくれます。
じゃあ毎年、冬至がまったく同じものなのか? なにか今年の特徴はないのか…、感じてみました(^◇^)
私のチャネリングでは、今年の冬至は…
【遥か】【整理】
ということばが出てきました。
遥か=隔たりのあるもの。それは心の内の隔たりです。
分裂している思い、自分の内が分離していくような感覚です。。
ああでもない、いやこっちでもない、自分が自分でなくなったり、自分がわからなくなったり、そんなことはなかったでしょうか。
今年の冬至は、そんな自分の中の隔たりを融合していく…、
そういったことに適しています。
ご自分の中心軸に入りましょう。揺るぎない状態へと整いやすくなると想います。
そして冬至のエネルギーを感じながら
ご自分の中心軸のエネルギーがどこまでも〜遥かなる隔たりまで〜広がっていく♪
そんな瞑想をしてみましょう。妄想でOKです。
内側が整って、そこからご自分の一陽来復が叶っていくことでしょう。
秋の季節に
2016/08/088/7の朝に土用は明け、暦のうえでは秋に入りました。
今年は大変な猛暑〜酷暑で、まだまだ猛暑真っ最中(汗)
どこに秋なんてあるんだろう・・・?って茫然としてしまいますが
私はおととい、夕立のあと、“ツクツクボウシ”を聞きました♪
夏至(6月20日頃)をピークに高かったお日さまも、部屋の端に日差しが入るようになってきました。
大阪では19時をまわると薄暗くなってきます。
もうそろそろ、、トンボさんも増えてくるかな。
もう秋なんです〜!!と言いたいんですが、まっだまだ!!
まず「気配」、「気」ですね。「気」から変わって「暑さ」があとからやってきます。
立秋の「立」は始まるという意味で、秋のはじまりを意味します。
涼しさは感じれなくても、空が高く感じたり、お月さまが明るく凛とみえませんか…☆
今年の暑さは格別ですが、本来なら「立秋」は秋季のはじまりで、
気候も暑さから寒さへ変わる重要な時期!「陽」から「陰」に変化していくのですね。
人のカラダも心も季節の影響を受け、
「秋」は、人間の臓器で言うと、肺や大腸の季節になります(中医学より)。
カラダの症状でいえば、セキや鼻水、肩背中のコリや疲れ…
メンタルでいえば、たとえば大泣きしたときや、あるいは声を殺して泣いたとき、、、
胸が苦しくなりますね。(;_;)胸には「肺」があります。悲しみは肺を傷つけやすいようですね。
肺の気のバランスが「マイナス」に傾くと、忍耐力・自分や物事を受け入れる受容力が低下して
悲しみが沸いてきやすくなります。
「ものおもいにふける秋」「物憂げな秋」と言われるのも、なんだか納得です。
こんなときは、心を安定に、気持ちを穏やかにして、こころを調整することを優先しましょう。
秋が進むと、稲穂が黄金色に実り、街のあちこちにも“小さい秋”が発見できますが
実はこれも秋の「気」のひとつで、草木を枯らす厳しい秋気があるのですが、それが働いたのです。
もしこれが悲しく傷ついた心に入ってしまうと、秋気で心が「枯れて」しまいます。。
なにか、悲しく感じるできごとがあっても、秋の風に流してもらい、高い空に空中分解するといいですね。
学校で言えば二学期。一番深まり盛り上がるころですね。
自然界でも、すべてのものが成熟し、容(かたち)が定まります。
まだまだ暑いさなかですが、深呼吸して心を養生し、実りの秋に向けて深まっていきたいですね。
土用の過ごしかた*ヒーリング式*
2016/07/13久しぶりのコラム更新です。
今年は、7月の声を聞いたとたん、天神祭の頃のような暑さがやってきて…体がついていけない〜(@_@;)
そんな方も多かったのでないでしょうか?
天神祭の頃は・・・暦のうえでは「土用」です。
もうすぐ夏の土用がやってきます!
今年の夏土用は
7月19日(火)〜8月6日(土)
(正確には、7月19日(火) 15:03 〜 8月7日(日) 10:53)
土用と聞くと、どんなイメージがあるでしょうか。
季節の変わり目、不安定、バランスを崩しやすい、… など黄信号のような時期ですね。
特に夏の土用は、暑さとあいまって一番凌ぎにくい時期でもあります。

まず「土用」とは・・・
今年の冬至は‥
2014/12/09冬至
先のコラムで少しふれた冬至ですが、より詳しく語りますね!
現代は、元旦がそれに当たりますが、かつては冬至が一年の始まりでした。
ご存じのように冬至は一年で最も昼が短く・夜が最も長い日。
昔の人々は、生命の終わる時期=「死に一番近い日」と考えていて
その厄を払うためにかぼちゃやお汁粉を食べ、体を温めることで栄養を取り、無病息災を祈っていました。
この習わしが現在でも続いています。
2014年、冬至を迎えるのは 12月22日 AM 8:11(日本時間)
弱まっていた太陽のチカラがこの日を境に復活し、エネルギーが陽に転じます!楽しみです☆☆
しかも今年の冬至は・・・朔旦冬至(さくたんとうじ)
聞き慣れない言葉ですが、実はたいへんおめでたいレアな冬至です。
朔旦冬至(さくたんとうじ)
「朔」は新月。「旦」は朝や夜明け、つまり太陽が昇ってくるとき。
月は‥
満月からどんどん欠けていき、やがて空から姿を消してしまいますが、新月でまた再び復活して毎日少しずつ満ちていきます。
太陽は‥
夏至からどんどん日が短くなり、冬至に向けて太陽の力が弱まっていきますが、ピークに達した冬至から太陽の力が復活し日が長くなっていきます。
ところが月の満ち欠けひとめぐりのサイクルは29.5日なのに対して、冬至から冬至までのサイクルは365日と異なるため
両者が重なることは非常に少なく、前回は19年前の1995年。
2014年の冬至は・・・
太陽が復活するおめでたい日 と 月が復活するおめでたい日 が重なります。
これを「朔旦冬至」と言い、めったに訪れることのない大変おめでたい日とされ、宮中などでも宴が催されていたといいます。
一陽来復(いちようらいふく)
陰が極まって、再び陽にかえるという意 。冬至にピッタリの言葉ですね。
「不運が続いた後、幸運に向かう。運気が上向く。」という意味合いがあります。
冬至の日を境に運気が上がるので、昔から「大切な日」とされてきました。
世界各地でも、冬至(あるいは、冬至から翌日にかけて)に、冬至祭が祝われます。
太陽の力が最も弱まった日を無事過ぎ去ったことを祝う日で、実はクリスマスの起源も冬至祭(ユール)だそう。
新たな流れが始まります。運気上昇の流れに身を委ねて、安心して進みましょう(^◇^)
冬至の日に食べると運気が上がるもの
春の七草同様、冬至にも病気にならないために体に良いとされている食べ物が7つあります。
かんてん、うんどん(うどん)など・・・。さぁ^^あと5つ写真から探してみましょう!
( にんじん・ぎんなん … )
名前の中に 「ん」 が2つ付くものは、「運気」「根気」 の 「ん」 が2つ入っていて 「運盛り」 と呼ばれ
食べることで運気と根気がつきます。
さらに冬至に 「ん」 のつくものを食べると 「運」 が呼びこめると言われています。
冬至七草 全部食べるのは大変ですが、せめてひとつは食べたいですね^^
冬至の日に入る“柚子湯”
ゆず湯の「ゆず」=「融通」がきく 冬至=「湯治」 という語呂合せもあることから
冬至の日に柚子湯に入る と思っている人も多いようですが
ゆず湯は本来「一陽来復」 に備え身を清めたと考えられ、運をよびこむ前の厄祓いから始まりました。
昔は毎日入浴する習慣がなく、そのため運を呼びこむ前に体を清めて厄祓いするための禊(みそぎ)として行ったようです。
現代でも、新年や大切な儀式に際しては入浴することがありますね。
もちろん、柚に「融通〔ゆうずう〕が利きますように」という願いが込めるのもいいでしょう。
また、冬至にゆず湯に入ると1年間風邪をひかないといわれています。
ゆず湯には、血行を促進することで冷え性を緩和する。身体を温めて風邪を予防するなどの働きがあるからです。
また、果皮のクエン酸・ビタミンCは美肌効果、ゆずの芳香はリラックス効果も期待できます。
今年の冬至は‥運を呼び込む前に、柚子湯に入り身体を清めて厄払いするといいですね☆
今年の冬至がみなさんの新たなスタートとなりますように‥☆
太陽もお月様も応援していますよ^^
太陽の光を浴びて心身元気に!
2014/12/09このコラムを書いているのが12月8日。
1年で最も日照時間が短い「冬至」が、今年は12月22日なので
ピークへと向かっている今が一番、お日様が恋しいのかもしれません。
著者も以前、この時期になると鬱的になっていたのを思い出します。
関西地方は17時前にもなると、本当につるべ落としのように‥いきなり暗がりに転換。
気が付くと街はどこも点灯され、なぜか気忙しくもなって…。
幼い時に入院したのもこの時期だったでしょうか?
季節的ウツという症状もあり、日照時間の短いこの時期に心の病が発症する方もいらっしゃるようです。
冬至まであともうちょっと…と言い聞かせながら凌いでいる今日このごろ。
人間だけでなく動植物も同じですが、私たちは太陽の恩恵によって生かされています。
太陽がないと作物は育たないし、あらゆる生命を生み育んでくれる大いなる源です。
太陽の光には、生命エネルギーである“氣”が含まれているのですね。
あらためて“氣”というのは「心と体の両方に活力を与えるエネルギー」のことです。
日中に太陽の光を浴びて氣が補充されますが、日没から減少しはじめて、夜明け前には欠乏状態になります。
夜中になると嫌なことを考えたり気が滅入りやすくなるのは、“氣”が不足するからだそうです。
では、日照時間の短いこの時期に、気が滅入らないようにするには…
・できるだけお昼間のうちに太陽の光を浴びておきましょう!(窓から差し込む光でも十分!)
(氣がわからなくても…『この太陽の光が元気の素!』という認識と感謝があればOK!)
・陽射しの気持ちよさや風景をできるだけ、記憶に焼き付けましょう。
↓
・夜になってもし気分が下がったときは‥それを思い出しましょう♪できる範囲でOKです。
次にぼんやりとイメージしましょう^^
〜太陽のひかりを〜 全身に浴びて〜 陽射しの気持ちよさを〜 感じてみましょう〜
〜さぁ今〜 どんな風景ですか〜 どんな温かさでしょうか?
太陽の陽射しを気持ち〜く浴びている〜
風景や温かさを〜
ありありと感じましょう。
これが習慣化されると‥
心の中に太陽が宿り、いつでもあなたの内側から“光”を引き出せますよ☆
もうすぐ冬至がやってきます!冬至を起点にまた日が長くなります。
今年の冬至は、またまたレアで、19年に一度の『朔旦冬至』(さくたんとうじ)。
太陽のお誕生日と月のお誕生日(新月)が同じ日なのです。
ダブルの夜明けの12月22日、とっても希望が湧いて楽しみです!

ヒーリングサロン オフィーリア
まずはお気軽にお問い合わせくださいね。
電話番号:090-1023-3593
所在地:大阪市住吉区長峡町2-1
営業時間:12:00〜18:00
(時間外応相談)